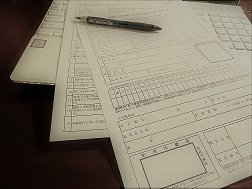公共事業に参加したい!
国・都道府県・市区町村が発注する建設工事・物品の購入等・役務の提供・測量・建設コンサルタント・業務委託などを直接請負いたい場合、入札参加資格審査申請書という書類を受付期間中に提出します。
多くの場合は、年明け早々の極寒の時期から春になるまでの間に提出の受付が為されます。
定期受付は、隔年が多いです。
定期受付に間に合わなかった場合、追加受付・随時受付等、提出先によって受付のスタイルに相違がありますが、定期受付を逃しても申請書の受付はしていただけることが殆どです。
この申請書は、
受付する国家機関・地方自治体によってルールが全然違います。
独自様式というものが大体の提出先に存在いたします。
添付書類に関しても、え?コレを添付するの?とビックリすることが結構ございます。
一般的に、都道府県内・市区町村内業者様に対して提出書類の種類が多くなる傾向にあります。
都道府県外・市区町村外業者様にはよほどのことがない限り、発注することがないという前提だからです。
できるだけ地元の業者様に!という地域密着型です。
しかし、その業者様しか展開していないレアな業務の場合は、この限りではありません。
実際、当事務所のお客様でも県外からバンバン受注されている業者様もいらっしゃいました。
提出に際して&省庁への申請
これは、各自治体によって相違があります。
市区町村レベルの地域超密着型の場合、新設法人については
平均完工高を算出できる状態でなければNGという市区町村と、
設立後満2年以上経過していなければNGという市区町村がございます。
要するに、工事実績がないのなら参加してくれるな。ということです。
設立後満2年以上〜という市区町村は、
他の業者様と同等の数値が出せるようになるまで待ってほしいということでしょう。
実績0で出されても判断に困る、ということは容易に想像がつくかと思います。
都道府県レベルの地域密着型の場合は、新設法人でも経審を受審できることから、少し緩和されます。
ただし、点数については各項目のほとんどが最低点になるため、「名前を売り込むために提出」というスタンスになります。
省庁インターネット一元申請(建設工事)
定期申請は、西暦偶数年の11月〜翌年1月中旬までです。
12月の庁舎最終稼働日までに、パスワードの取得及び代理申請の場合の委任状送付をしなければ、本申請はできません。
委任状については、自署+捺印です。
申請データ及び消費税の納税証明書その3関連は、受付期限までに送信できればOKです。
ただし、システムの稼働時間は
9:00〜17:00
例え入力中でも17:00ピッタリにシステムは落ちますのでご注意を。
定期受付に間に合わなかった!
随時受付を行っておりますので申請はできます。
ただし、定期受付期間以外はインターネット受付を行っておりません。
郵送またはメールでの申請となります。
|
申請先一覧 |
|
国土交通省大臣官房会計課所掌機関 |
|
国土交通省地方整備局 |
|
国土交通省北海道開発局 |
|
法務省 |
| 財務省財務局 |
|
文部科学省 |
|
厚生労働省 |
|
農林水産省大臣官房予算課 |
|
農林水産省地方農政局 |
|
農林水産省地方農政局 |
|
林野庁 |
|
経済産業省 |
|
環境省 |
|
防衛省 |
|
最高裁判所 |
|
内閣府 |
|
内閣府沖縄総合事務局 |
|
東日本高速道路(株) |
|
中日本高速道路(株) |
|
西日本高速道路(株) |
|
首都高速道路(株) |
|
阪神高速道路(株) |
|
本州四国連絡高速道路(株) |
|
独立行政法人水資源機構 |
|
独立行政法人都市再生機構 |
|
日本下水道事業団 |
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
統一資格審査申請・調達
物品の販売や買い受け、役務提供に関する入札参加を希望する場合に申請します。
省庁の物品製造等は、新設法人でも提出可です。
定期受付は、3年毎です。最近では、令和4年に行われております。
定期受付に間に合わなかった場合は、随時受付で申請が可能です。
内容については、下記の通りです。
| 資格の種類及び調達する物品等の種類 |
|---|
| (1) 物品の製造 | ||
|---|---|---|
|
1.衣服・その他繊維製品類 |
2.ゴム・皮革・プラスチック製品類 |
3.窯業・土石製品類 |
|
4.非鉄金属・金属製品類 |
5.フォーム印刷 |
6.その他印刷類 |
|
7.図書類 |
8.電子出版物類 |
9.紙・紙加工品類 |
|
10.車両類 |
11.その他輸送・搬送機械器具類 |
12.船舶類 |
|
13.燃料類 |
14.家具・什器類 |
15.一般・産業用機器類 |
|
16.電気・通信用機器類 |
17.電子計算機類 |
18.精密機器類 |
|
19.医療用機器類 |
20.事務用機器類 |
21.その他機器類 |
|
22.医薬品・医療用品類 |
23.事務用品類 |
24.土木・建設・建築材料 |
|
25.警察用装備品類 |
26.防衛用装備品類 |
27.その他 |
| (2) 物品の販売 | ||
|---|---|---|
|
1.衣服・その他繊維製品類 |
2.ゴム・皮革・プラスチック製品類 |
3.窯業・土石製品類 |
|
4.非鉄金属・金属製品類 |
5.フォーム印刷 |
6.その他印刷類 |
|
7.図書類 |
8.電子出版物類 |
9.紙・紙加工品類 |
|
10.車両類 |
11.その他輸送・搬送機械器具類 |
12.船舶類 |
|
13.燃料類 |
14.家具・什器類 |
15.一般・産業用機器類 |
|
16.電気・通信用機器類 |
17.電子計算機類 |
18.精密機器類 |
|
19.医療用機器類 |
20.事務用機器類 |
21.その他機器類 |
|
22.医薬品・医療用品類 |
23.事務用品類 |
24.土木・建設・建築材料 |
|
25.警察用装備品類 |
26.防衛用装備品類 |
27.その他 |
| (3) 役務の提供等 | ||
|---|---|---|
|
1.広告・宣伝 |
2.写真・製図 |
3.調査・研究 |
|
4.情報処理 |
5.翻訳・通訳・速記 |
6.ソフトウェア開発 |
|
7.会場等の借り上げ |
8.賃貸借 |
9.建物管理等各種保守管理 |
|
10.運送 |
11.車両整備 |
12.船舶整備 |
|
13.電子出版 |
14.防衛用装備品類の整備 |
15.その他 |
| (4) 物品の買受け | |
|---|---|
|
1.立木竹(ただし、国有林野事業で行う林産物の買受けを除く。) |
2.その他 |
| 申請先 | |
|---|---|
|
衆議院庶務部会計課長 |
参議院庶務部会計課長 |
|
国立国会図書館総務部会計課長 |
最高裁判所事務総局経理局長 |
|
会計検査院事務総長官房会計課長 |
内閣府大臣官房会計課長 |
|
デジタル庁会計担当参事官 |
復興庁会計担当参事官 |
|
総務省大臣官房会計課長 |
法務省大臣官房会計課長 |
|
外務省大臣官房会計課長 |
財務省大臣官房会計課長 |
|
文部科学省大臣官房会計課長 |
厚生労働省大臣官房会計課長 |
|
農林水産省大臣官房参事官(経理) |
経済産業省大臣官房会計課長 |
|
国土交通省大臣官房会計課長 |
環境省大臣官房会計課長 |
|
防衛省大臣官房会計課長 |
添付書類
1.登記事項証明書の写し(法人)
2-a.財務諸表(法人)
2-b.営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人)
3.次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書の写し(電子納税証明書含)
A 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
(個人の場合はその3の2、法人の場合はその3の3)
B 法人税(法人)
C 所得税(個人)
静岡県の場合
建設工事
静岡県に入札参加資格申請をする場合、原則として電子申請とされております。
定期受付は隔年。受付期間は、約1ヶ月。定期受付は隔年で、申請期間は11月半ばから12月半ばまでとなります。
それ以外の受付は随時です。
経審では、審査基準日を重視し、それに沿って審査書類をチェックしていきますが、入札参加資格申請の場合は決算期は重視しておりません。
所定の期間内に経審を受審していることが申請の条件となります。
電子申請の場合は、経審の結果通知書の添付は不要です。
その他、事業所の状態においては、申請年の12月31日時点での見込みを記載すること、工事経歴書の記載は決算期内のものでなくてもOK、など、期間の区切りが項目によって違います。
申請し忘れた!
その場合は、年明けに開始される紙申請で対応することになります。
決算期毎に提出日が決められております。受付場所は県庁のみとなっております。
維持管理業務
市町等への申請の場合、建設工事で入札参加資格申請をすれば、維持管理業務も含まれることが殆どですが、県への申請の場合、維持管理業務は別枠となりますのでご注意ください。
その他、入札参加資格申請の種類には
建設コンサルタント、物品・一般業務委託(有効期間3年)、庁舎等管理業務の委託、情報システム開発(有効期間3年)があります。
市町等の受付スタイル
2年に一度(オモテ年・ウラ年と言われているうちのオモテ年)実施されます。
申請書の有効期限は2年です。
ウラ年の受付です。有効期限は1年間です。
定期受付提出要領公開のおよそ1年後に各自治体のHPにて提出要領が公開されます。
追加受付には定期受付同様提出期限があり、
受付期間が終了すると提出要領もろともHPから削除されることが殆どです。
来年のために提出要領を確認しておこうかな〜。と思ってもできません。
寒くなってきたな〜と思ったら、忘れずにチェックしましょう。
定期受付が終了してから次の定期受付までの間、いつ提出してもOK!というとても柔軟性のある制度です。
従って、提出要領もいつでも確認できます。
毎月業者登録が行われていることが多いので例えば、定期受付が令和2〜3年度の場合、業者登録日から令和4年の3月31日まで有効となります。
提出が後になればなるほど、有効期限は短くなります。
入札参加資格の種類
建設工事・物品の購入・役務の提供・測量・建設コンサルタント等に分類されます。
建設工事に付随するような業務委託は、建設工事の入札参加資格申請が為されていれば大体は発注されます。
建設工事
経営事項審査は、官公庁が発注する建設工事の入札参加資格申請のために受審している業者様が殆どです。
各官公庁によって基準の相違はありますが、業者様に対してのランク付(格付け)が行われます。
格付け業種について、静岡県内では 土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事の4業種がメジャーですが、他県を覗いてみると 舗装工事や造園工事、塗装工事・防水工事・水道施設工事も対象になっている市町もございます。
ランク付の対象になるものを一部抜粋致しますと
等...挙げればキリがありませんが、
経審の結果通知書がすべてではない、ということです。
詳細は、また別記いたします。
物品の購入・役務の提供
こちらは、官公庁に納入する物品や、清掃や点検などの役務の提供を希望する場合に申請します。
建設工事は、業種は29が上限でそれ以上はありませんが、物品・役務提供に関しては実に様々な品目がございます。
そして、分類の仕方も各自治体によって全然違います。
各品目の2年平均売上額や年間売上高の記載を求める自治体もあります。
入札希望の品目の分類が、A市はその他一括でよかったのに、B市は分類1だった。C市では分類3だった。ということはザラです。
複数の自治体に提出する場合、金額を1から拾い直すことも日常茶飯事です。
建設工事よりも手間がかかりますね。
測量・建設コンサルタント
こちらは、測量業者・土木関連の建設コンサルタント・建築士事務所・地質調査業者等が公共事業に参加したい場合に申請します。
司法書士や土地家屋調査士も参加可能です。
提出書類
自治体によって相違はございますが、共通しているものを挙げてみます。
各機関指定の様式で作成します。
市区町村は独自様式が存在することが多いです。
全国統一様式という書式もあるのですが、現在こちらは主に国の機関に提出する際のみ使用、でしょうか。
昔は申請書については全国統一様式を使用、添付書類や独自審査事項で各自治体のカラーを出してるな〜という感じでしたが、今は殆ど独自様式の申請書になっているようですね。
最近では、電子申請で受付している自治体もございます。
これは全国共通ですね。
自治体によっては、この内容を独自様式に転記して提出させる事もあります。
結果通知書を添付するにも関わらず。です。
業種によっては、各自治体で格付けしているものもあるので、その格付けの際の必要書類の一つであります。
格付けは、毎年実施・定期受付の年に2年縛りで実施等、各自治体で相違があります。
2年縛りなら、経審も毎年受けなくても2年に一度でいいじゃん!
とお思いになるかもしれませんが、それはNGです。
入札参加資格申請書の提出は隔年ですが、経審の結果通知書の有効期限は1年7ヶ月なのです。
従って入札参加資格登録をしている役所に対して、毎年提出しなければなりません。
経審は、毎年受けてナンボです。
市区町村に入札参加資格申請書を提出する場合、決算終了後の変更届出書で作成したものの写しを提出、とされていることが多いです。
経審の結果通知書に合わせる、という意味と、入札参加資格申請のための脚色は禁止!という意味もあるかと思います。
都道府県に提出、となると直近までの工事経歴を加筆してもOK!と少し柔軟な対応になったりします。
申請書や誓約書に押印する印鑑は、法人であれば法務局に届出している印鑑、個人であれば当事務所では実印を押印して頂いております。
この使用印鑑届には、契約に使用する印鑑を押印します。
○□2つの枠があります。
○枠には丸印、□枠には角印(使用しない場合は空欄でOK)を押印します。
法人の場合、実印は
どうしても実印を使用しなければいけない書類にしか押印しない、という方も一定数いらっしゃるため、(実印以外の社印も保有)『どういうハンコを押せばいいの?』という問い合わせを頂くことがございます。
ハイ。契約に使用する印鑑をお願いします!
こちらは税務署で発行される納税証明書です。
その3の2は、個人事業者の所得税及び消費税の未納がないことの証明書
その3の3は、法人の法人税及び消費税の未納がないことの証明書
経営事項審査で提示する、納税証明書その1(消費税)は、納付税額が記載されていますが、その3関連は税額の記載はございません。
未納の有無が焦点となっております。
契約を締結する営業所の所在地である市区町村の税金に未納がないかどうかを確認する証明書です。
税金に未納がある場合はこの証明書は出ません。
税金に未納がある業者様は、入札参加資格の対象外、ということになります。
個人事業者の場合は身分証明書の写し、法人の場合は履歴事項全部証明書の写し
提出先によって相違がございますが、当事務所の実績から抜粋しますと
事業税の納税証明書
建設業の許可を受けていることを証明する書類(許可通知書・許可証明書)
ISO関連・エコアクション21関連の書類
といったところです。
当事務所の実績としては、物品・役務提供についての作成及び提出実績は多数ありますが、測量・建設コンサルタントは殆どございません。
建設工事以外の場合、申請書・誓約書・使用印鑑届などは建設工事と同様ですが、求められる添付書類が多少変わって参ります。
主には、会社のパンフレットや営業資格を要するものであるならば、その資格証の写しでしょうか。
建設工事の場合は、工事実績については決算終了後の変更届出書で作成しますのでそれを提出しますが、物品・役務提供の場合、実績調書については1から起こさなくてはなりません。
自治体によって分類の仕方が違うので、実績調書作成と合計金額算出が一番手間がかかります。
格付け
格付けは、特定の業種について行われます。
静岡県では、土木一式工事業・建築一式工事業・電気工事業・管工事業の4業種について格付けが行われています。
建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領では次のように定められております。
この要領は、建設工事の競争入札に参加することができる資格を有する者の格付及び建設工事の競争入札に参加させようとする者(随意契約において見積書を徴しようとする者を含む。以下同じ。)の選定等について他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
提出後、仕事を取るために
現在は新規申請の際に電子入札に参加するためのIDとパスワードが付与されます。
このID及びパスワードは業者様が直接受け取る形になります。
ICカード及びカードリーダーは各自設置することになりますが、認証局が複数ある上にICカード・カードリーダーの価格もバラバラです。
こちらでご確認ください。認証局一覧
電子入札は、○ん○○を回避するために導入されたシステムです。
最初の設置完了までは手間がかかりますが、頑張りましょう。
やはり積算ソフトは必要になってきますね。
しかし、かなり高額なのがネックです。
でも、補助金があるんです^^
それから、公共工事を請け負うようになると工事実績情報システム(Construction Records Information Systems通称:CORINS)に工事カルテ及びそれに関するデータを提出しなければなりません。
税込500万円以上の工事から登録が可能になります。
税込2,500万円以上の工事については、登録が義務付けられております。
詳細は、こちらからどうぞ。
更に、建設リサイクルが絡んでくると、建設副産物情報交換システム(COBRIS)への報告も必要になってきます。
さて、新規で提出してから仕事が入るようになるまでの期間ですが、
昔は最初の2年で入ることは皆無でした。
3年目からぼちぼち入るようになった、という話をよく耳にしました。
しかし、3年目から仕事を受注できるようになった業者様は営業活動に力を入れていたパターンが多いです。
役所の各課に業者様の名刺はこちらへと書かれたBOXがカウンターに設置されている場合がございます。
名刺の数が多い=足を運んだ回数が多い。ということになります。
営業活動をまったく加味しない自治体もございますが、名刺の数を評価してくださる自治体も少なからず存在します。
年度が変わると名刺をごっそり手に持ち、片っ端から名刺BOXに入れていく方をよく見かけます。
現在では2年待たなくても入ることもあるようですが、これも地域によるんでしょうね。
以上のことから、参加資格申請を提出してから最初の仕事を落札するまでには、ランニングコストがかかるということをご理解いただけると思います。
カードリーダーの設置、名刺配布の営業、積算ソフトの購入、更には格付けされる業種の場合は自社のランクにも気を配らなければなりませんし、全てが紙と対面で行われていた時代とは全く違います。
これらの事項も踏まえた上で、入札参加をするか否か、ご検討いただければ幸いです。
ある程度、仕事が取れるようになってくると、このような問題にぶつかります。
その場合、新しく入社した有資格者や技能者の割り当ては可能ですか?というお問合せをいただくことがあります。
静岡県(発注の工事)の場合、入社して3ヶ月経過後から可能となります。
経審では、入社して6ヶ月と1日以上経過しないと技術職員名簿に記載できないという点から見ると、これはかなり寛大な設定だと思います。
市区町村については、各自治体によって相違があるものと思われますので、担当部課にお問合せください。
当事務所では
実績は多数ございますが、忘却の彼方に消えてしまったものもまた、多数ございます。
提出先実績としては
省庁(建設工事・物品)・静岡県(建設工事・維持管理業務・物品・庁舎等管理業務の委託)・富士市・岳南排水路管理組合・富士宮市・沼津市・三島市・駿東郡清水町・駿東郡長泉町・駿東郡小山町・裾野市・御殿場市・田方郡函南町・伊豆の国市・伊豆市・賀茂郡東伊豆町・賀茂郡西伊豆町・賀茂郡河津町・伊東市・熱海市・下田市・静岡市・焼津市・藤枝市・掛川市・浜松市・甲府市・山梨市・山梨県南巨摩郡南部町・山梨県南巨摩郡身延町・山梨県南都留郡山中湖村・山梨県西八代郡市川三郷町・大月市・甲斐市・富士吉田市・駿東伊豆消防本部・(現在は省庁ネット一元に含まれますが)紙申請の時代の横浜防衛施設庁・東海北陸医務局 等
思い出したら随時追加していきます。